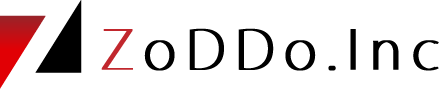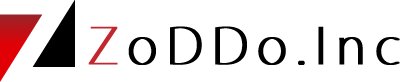2025.9.3
飲食店が3年で潰れるワケ|失敗オーナーの特徴とパターン

こんにちは!
名古屋でホームページ制作を行う株式会社ZoDDoです。
当社では独立開業される方からの集客に関するご相談・ご依頼を頂きます。
クリニック、美容院や企業もありますが、飲食店の方も多くいます。
飲食店の開業は夢を実現する第一歩ですが、現実には3年以内に約6割が廃業しているという統計があります。
10年以上コンサルタントとして経営支援をしてきた経験から言えるのは、失敗する人には明確な共通点があるということです。
本記事では、飲食店を開業して失敗する人の特徴や廃業の原因を整理し、成功のためのポイントをわかりやすく解説します。
飲食店開業の現実と失敗率のデータ
飲食店は人気の開業業種ですが、その裏側には厳しい現実があります。
中小企業庁や商工会議所の調査によると、新規開業した飲食店のうち約6割が3年以内に廃業し、5年後にはおよそ8割が撤退していると言われています。
これは他の業種と比較しても高い割合で、飲食業界の競争の激しさを示すデータです。
私が10年以上、ビジネスコンサルタントとして飲食店オーナーを支援してきた中でも「勢いと情熱だけで開業したが、数年で赤字に転落した」というケースは少なくありません。
開業直後は新規顧客で一時的に売上が上がりますが、リピーターを獲得できなければ売上は下降線をたどり、やがて経営難に陥ります。
さらに、飲食店は「立地が良ければ成功する」という誤解も多いのですが、実際には事業計画の精度、メニューの設計、利益率管理の徹底が重要です。
例えば好立地でも家賃が高ければ固定費の負担が重くなり、利益を圧迫して赤字に直結することも珍しくありません。
つまり飲食店経営は「美味しい料理を提供する」だけでは成立せず、数値管理やリスク対策を行えるかどうかが成功と失敗の分かれ道となります。
失敗する飲食店オーナーの特徴
飲食店を開業して失敗するオーナーには、いくつかの共通点があります。
10年以上コンサルタントとして経営を支援してきた経験から、特に次のような特徴が目立ちます。
① 事業計画が甘い
「毎月これくらいは売上が上がるはず」と楽観的に見積もり、固定費や利益率を正しく計算していないケースが多く見られます。
特に家賃が高すぎる物件を契約し、利益を圧迫してしまう失敗は典型例です。数字を軽視した事業計画は、赤字経営の大きな原因になります。
② メニュー設計と原価管理の不備
「美味しい料理を提供すれば成功する」という思い込みで、原価率や粗利を無視したメニュー構成をしてしまうことがあります。
結果として、客数が入っても利益が残らず、経営が苦しくなるのです。
メニューは“人気”だけでなく“利益率”も同時に考えなければなりません。
③ 立地依存の思い込み
「駅前だから成功する」「人通りが多ければ集客できる」といった立地への過信も危険です。
実際には、店舗コンセプトと立地条件が一致しなければリピーターは定着せず、固定費だけが重荷になるのです。
④ 数値管理を怠る
飲食店は売上、食材ロス、人件費率など日々の数値管理が欠かせません。しかし、料理や接客に注力しすぎて数字を分析しないオーナーは、赤字に気づくのが遅れがちです。
感覚頼りの経営では廃業のリスクが高まります。
廃業につながる主な原因
飲食店が廃業に至る背景には、共通する原因があります。
10年以上コンサルタントとして多くの店舗を見てきた経験から、特に以下の4点が大きな要因となっています。
① 家賃や人件費など固定費の重さ
飲食店経営で最も大きな負担となるのは家賃と人件費です。
都市部の好立地は人通りが多い反面、家賃が高額で利益を圧迫します。また、人材不足による人件費高騰も経営を直撃します。固定費が売上を上回れば、どれだけ忙しくても赤字から抜け出せません。
② 赤字を放置する経営判断の遅れ
「今だけの赤字だから」と改善を先延ばしにするオーナーは多いですが、これは大きなリスクです。
原因を分析せずに放置すれば、資金繰りが悪化し、キャッシュフローが尽きて廃業に直結します。早期の修正こそが生き残りのカギです。
③ 集客戦略の不在
現代の飲食店は「立地に任せれば客が来る」時代ではありません。
SNSや口コミ、地域密着の販促活動を行わないと、集客は一過性に終わり、リピーターが定着しません。集客の仕組みを持たない店舗は、安定した売上を確保できず経営が不安定になります。
④ 流行に依存したメニュー戦略
流行の波に乗って一時的に売上を伸ばすことはできますが、ブームが過ぎると客足は一気に減少します。過去の「タピオカブーム」などが典型例です。
長期的に支持されるメニュー設計を欠いた店舗は、継続的な経営が難しくなるのです。
成功する飲食店との違い
飲食業界の中でも、安定して利益を出し続ける店舗には共通点があります。
失敗する店舗との最大の違いは、「経営を感覚ではなく仕組みで回しているか」という点です。
① 明確なコンセプトとターゲット設定
成功している飲食店は「誰に、どんな体験を提供するのか」を明確にしています。
例えば「子育て世代が安心して利用できるカフェ」や「仕事帰りのビジネスマンが短時間で利用できる定食屋」など、ターゲットがはっきりしているのです。
コンセプトが曖昧な店舗は差別化ができず、リピーターを獲得できません。
② 利益率を重視したメニュー設計
成功店は原価率を管理しながら、売れるメニューと利益を確保できるメニューをバランス良く構成しています。
例えば原価率30%前後を目安にしつつ、粗利が高い商品を軸に客単価をコントロールします。「美味しい」だけでなく「利益が残る」メニュー設計が、継続経営のカギです。
③ 立地に合わせた店舗戦略
立地が良いだけでは成功しません。成功店は「駅前なら回転率重視」「住宅街なら家族利用重視」といったように、立地条件に最適化した戦略を取ります。
場所に応じた経営方針を組み立てられるかどうかが生き残りの分岐点です。
④ 数値管理と改善を習慣化
売上、利益率、客数、リピート率などの数値を定期的に分析し、改善策を打ち続けることも成功店の特徴です。
例えば「曜日別の売上データをもとに、閑散日に限定メニューを導入する」といった工夫です。データに基づいた経営判断を継続できるかどうかが、長期的な存続を左右します。
廃業を避けるための改善策とまとめ
飲食店の廃業率が高いのは事実ですが、適切な対策を取れば生き残ることは十分に可能です。
10年以上のコンサルティング経験から見ても、以下の改善策を徹底している店舗は安定経営につながりやすいといえます。
① 事業計画書を作成し、定期的に見直す
開業前に利益率や固定費をシミュレーションした事業計画書を作成し、開業後も定期的に見直すことが重要です。
特に、家賃・人件費・食材原価を定量的に把握し、赤字の兆候を早期に察知できる体制を作ることが必要です。
② 固定費と利益率の徹底管理
家賃比率は売上の10%以内、人件費率は30%以内、原価率は30%前後が理想的な目安です。これらを超えると赤字リスクが高まるため、数値管理に基づいた経営判断が欠かせません。
③ 集客戦略を仕組み化する
一過性の集客に依存するのではなく、リピーターを獲得する仕組みを作る必要があります。
具体的には、SNS運用・口コミ強化・地域密着型のキャンペーンなどを組み合わせることです。新規顧客を呼び込みつつ、再来店を促す仕掛けを持つ店舗は安定的に売上を維持できます。
④ データに基づいた改善サイクル
売上・利益・客単価・回転率などを日次・週次で確認し、改善策を即座に反映させることが成功のカギです。例えば「月曜は客足が少ないから限定メニューで集客を強化する」といった小さな改善の積み重ねが、大きな差を生みます。
⑤ コンサルタント視点からの提言
飲食店は「料理の腕前」だけで勝負できる時代ではなくなっています。
経営者としての数字管理・戦略立案・改善行動を日常的に実行できるかどうかが、廃業を避ける最大のポイントです。
今回のまとめ
飲食店が失敗に陥る背景には「事業計画の甘さ」「固定費の負担」「集客戦略の不足」「数値管理の欠如」といった共通点があります。
一方で、成功する店舗は利益率を意識した計画、立地に合わせた戦略、データに基づく改善を徹底しています。
飲食店を長く経営するためには、情熱だけでなく「数字と戦略に基づく経営力」が不可欠です。