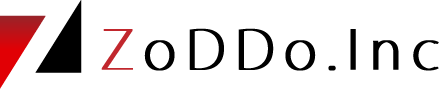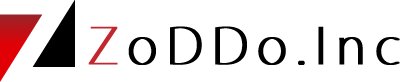2025.7.29
検索ボリュームの調べ方と選び方|SEOに強いキーワードの見極め方

SEO対策を成功させるカギは、適切なキーワードの選定にあります。
しかし、「検索ボリュームの多いキーワードを選べばいい」と考えるのは危険。
この記事では、検索ボリュームの正しい調べ方と、自社サイトの状況に応じたキーワード選びの方法を、初心者にもわかりやすく解説します。
Googleのツールや競合分析の活用法も含めて、WEBサイト運営に役立つ実践的なノウハウをお届けします。
関連記事
SEOに適したホームページ制作について目次
キーワード選定のための検索ボリュームの調べ方
SEO対策で成果を出すには、まず「どんなキーワードで検索されているか」を正確に把握することが欠かせません。
その出発点が「検索ボリュームの調査」です。
このブロックでは、キーワード選定のステップに沿って、検索ボリュームの正しい調べ方を解説します。
メインキーワードの選定
最初に行うべきは、メインキーワードの設定です。
これは、あなたのWEBサイトやビジネスが提供しているサービス・製品に関係する、もっとも基本的で核となるキーワードのことです。
例えば、ホームページ制作会社であれば「ホームページ制作」「WEBサイト構築」「SEO対策」などが該当します。
ここで重要なのは、自社が発信したい言葉ではなく、ユーザーが実際に検索しそうな言葉を選ぶことです。
また、メインキーワードを選定する際には、共起語の存在も見逃せません。
共起語とは、あるキーワードと一緒に使われやすい単語のことです。
「SEO」というキーワードに対しては、「Google」「検索順位」「キーワード分析」などが共起語となります。
共起語の調査に使えるツール例:
- ラッコキーワード
- ミエルカ(コンテンツ設計向け)
- 共起語検索(Google Chrome拡張)
共起語を意識することで、検索意図の広がりや関連ワードを取りこぼさずに済み、SEOの精度が向上します。
複合キーワードのリストアップ
次に行うのが、複合キーワード(ロングテールキーワード)のリストアップです。
メインキーワードだけでは競合が強すぎて上位表示が難しいため、2語〜3語を組み合わせた具体的な検索フレーズを想定しましょう。
例:
- 「ホームページ制作 名古屋」
- 「SEO対策 方法 初心者」
- 「WEBサイト 集客 強化」
こうしたキーワードは検索意図が明確であり、ニーズの高いユーザーがアクセスする傾向にあります。
複合キーワード取得に便利なツール:
- Google検索のサジェスト(検索窓に入力すると候補が出る)
- ラッコキーワード(複合語の網羅に強い)
- Googleトレンド(検索動向を時系列で確認)
- Ubersuggest(ボリュームや難易度も表示される)
こうしたツールを活用しながら、ユーザーの視点で「どんな悩みを抱えているか」を想像し、キーワードを設計していきましょう。
検索ボリュームの調査
候補のキーワードが揃ったら、それぞれの検索ボリューム(月間検索数)を調べます。
これは、そのキーワードでどれだけの人がGoogle検索しているかを示す指標です。
検索ボリューム調査に使える代表的ツール:
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| Googleキーワードプランナー | 月間検索数、競合性、クリック単価(CPC)も表示。無料。 |
| Ubersuggest | 無料で使える範囲が広く、SEO難易度も表示される。 |
| KeywordTool.io | サジェストと一緒にボリューム表示。海外含め広範囲に対応。 |
| Ahrefs / SEMrush | 有料だが、競合サイト分析も可能で精度が高い。 |
Googleキーワードプランナーを使えば、検索数の目安(例:1,000〜1万)だけでなく、広告出稿時の競合性も分かります。これにより、キーワードの価値が見えてきます。
検索ボリュームの目安分類:
- ~100:ニッチ。立ち上げたばかりのサイト向け
- 100~1,000:中規模。初心者向けには狙いやすいゾーン
- 1,000~10,000:需要が高く競争も多い
- 10,000以上:ビッグキーワード。大手メディアや企業が狙う領域
ただし、検索数が多い=成果が出るとは限りません。
検索ボリュームとともに、「検索意図」や「競合性」をあわせて判断することが大切です。
以上が、検索ボリュームを調べるための基本的なステップです。
次のブロックでは、サイトの成長フェーズごとに「検索ボリュームの活用方法」を詳しく見ていきましょう。
【サイト状況別】検索ボリュームを活用したキーワード選定方法
検索ボリュームは、SEO施策における「地図」のようなもの。
ですが、その地図の使い方は、サイトの成熟度や成長段階によって異なります。
立ち上げ直後のサイトと、ある程度アクセスを獲得しているサイトとでは、狙うべきキーワードのボリュームや競合性も大きく変わってくるのです。
このブロックでは、サイトの成長ステージに応じた「検索ボリュームを活用したキーワード選定法」を解説します。
サイトを立ち上げてすぐはロングテールキーワード優先
新しく立ち上げたばかりのサイトにとって、いきなりビッグキーワードで上位を狙うのは至難の業。Googleの評価が定まらない段階では、ロングテールキーワード(複合キーワード)を中心に攻めるのが鉄則です。
たとえば、
- 「ホームページ制作」ではなく「ホームページ制作 名古屋 格安」
- 「SEO」ではなく「SEO 初心者 内部対策 方法」
このような具体性の高いワードは、検索ボリューム自体は小さいものの、検索意図が明確で購買・問い合わせにつながりやすいのが特徴です。
さらに競合も比較的少ないため、ドメインパワーが弱くても上位を狙える可能性があります。
アクセスが増えてきたらミドルキーワードにも挑戦
ある程度記事数が増え、毎月のアクセスも安定してきた段階では、月間検索数が1,000〜5,000程度の「ミドルキーワード」へのチャレンジが可能です。
このフェーズでは以下のような戦略が有効です。
- 既存記事をリライトして検索意図を拡張
- ロングテールから派生する関連キーワードを網羅
- 複数記事を内部リンクで連携させてテーマ性を強化
ミドルキーワードは検索ボリュームがそれなりにあるため、流入数の増加やブランド認知の向上にもつながります。
一方で競合も多くなるため、記事の質・網羅性・内部リンクの設計がカギになります。
ミドルキーワードで上位表示されるようになればビッグキーワードに挑戦
中堅以上のサイトになれば、いよいよ月間検索数1万以上の「ビッグキーワード」を狙う段階に入ります。
ただし、ビッグキーワードは上位表示されるまでに時間がかかるうえ、強力な競合サイト(大手メディア・企業)がひしめいています。
ここでは「競合分析」が不可欠です。
競合分析で確認すべきポイント:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上位表示されているサイトのドメイン(企業系/個人系) | 競合の強さを測る |
| 上位ページの文字数・構成 | どれくらい深く解説しているか |
| 含まれているキーワード・共起語 | 参考にできる内容を抽出 |
| 被リンクの数・質 | 外部対策の有無を判断 |
このような情報を元に、競合と差別化できるコンテンツを企画し、戦略的にSEOを展開していく必要があります。
また、Googleは「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を重視する傾向にあるため、専門家監修や実績の提示、信頼できる情報源へのリンクなども、コンテンツ強化には欠かせません。
検索ボリュームは数字で見えるものですが、「サイトの現状」や「検索意図」と組み合わせて考えることで、より効果的なキーワード戦略が実現できます。
次のブロックでは、なぜ検索ボリュームだけでキーワードを選んではいけないのか、その落とし穴について解説していきます。
検索ボリュームだけで判断してはいけない理由
検索ボリュームは、たしかにキーワード選定の指標として非常に重要です。
しかし、検索ボリュームの大きさ=成果の大きさではありません。
むしろ、ボリュームだけに注目してキーワードを選ぶと、思わぬ落とし穴にハマってしまう可能性があります。
このブロックでは、検索ボリュームに依存することのリスクや、成果につながるキーワード選定に必要な視点について解説します。
ボリュームが多くても成果に直結するとは限らない
月間検索数が1万を超えるような「ビッグキーワード」は一見魅力的ですが、実際にそのキーワードで上位を取れたとしても、アクセスだけで終わってしまうケースが多くあります。
たとえば、「WEBサイト」といった大きな単語は検索数も多いですが、検索者の意図はさまざまです。
- 情報収集(例:WEBサイトとは?)
- 制作依頼の比較(例:WEBサイト 制作会社 おすすめ)
- 自作したい(例:WEBサイト 作り方 無料)
このように、検索ボリュームが多いほど検索意図の幅も広くなり、コンバージョンに結びつきにくくなるのです。
ターゲット外のユーザーが流入してしまう
検索ボリュームだけでキーワードを決めると、自社のターゲットではない層からのアクセスも増えてしまいます。
結果的に直帰率が高くなり、Googleから「このページはユーザーの役に立っていない」と判断され、検索順位が下がるリスクもあります。
たとえば、あなたが企業向けにWEB制作を提供している場合、「ホームページ 無料 作成」といった検索ワードで上位表示しても、個人利用者や無料ツールを探している層が訪れるだけで、問い合わせにはつながりません。
キーワードは「誰に向けているのか?」を常に意識して選びましょう。
本当に重要なのは「検索意図」との一致
検索ボリュームの大小よりも大切なのが、検索意図との一致です。
検索意図とは、ユーザーがそのキーワードで何を求めているのかという「背景」です。
検索意図には以下の3つのタイプがあります:
| タイプ | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 情報収集型 | 知識を得たい | 「SEOとは」「WEBサイト 仕組み」 |
| 比較・検討型 | 選びたい | 「ホームページ制作 比較」「CMS 比較」 |
| 行動・購買型 | 行動したい | 「ホームページ制作 名古屋 おすすめ」「WEBサイト 制作 依頼」 |
このように、検索ボリュームが少なくても、検索意図と自社サービスが合致していれば、高いコンバージョン率が期待できるのです。
特に企業サイトやブログで成果を出したい場合は、ただ「見られる」だけでなく「読まれ、動いてもらう」ことをゴールにする必要があります。
検索ボリュームはたしかに便利な指標ですが、それだけを信じてキーワードを選んでしまうと、SEO施策の本来の目的である「成果につながる集客」が遠のいてしまいます。
次のブロックでは、競合サイトを分析して、どのように「狙い目キーワード」を見つけていくのかを紹介します。
競合サイトの分析でわかる狙い目キーワード
SEOで成果を出すには、「ユーザーが求めているキーワード」を探すだけでなく、「競合が取りこぼしているキーワード」を見つけることも重要です。
そこで有効なのが、競合サイトのキーワード分析です。
上位表示されているページは、どんなキーワードを使い、どんな構成で記事を書いているのか?
それを読み解くことで、自サイトに足りない視点や、逆に差別化できる切り口が見えてきます。
競合が多すぎるキーワードは避けるのが賢明
まず大前提として、検索結果の上位が「大手企業」や「ニュースメディア」「官公庁サイト」などで埋まっている場合は、新規参入しても太刀打ちできない可能性が高いです。
たとえば、「SEO対策」の検索結果には、大手ツール会社や専門メディアが並びます。
こうしたキーワードで上位表示を狙うには、強いドメインパワーや豊富な実績が必要になるため、時間もコストもかかります。
そのため、競合が弱い or 不在のニッチなワードや、「意図がズレたページが多い」キーワードを狙う方が成果につながりやすいのです。
競合サイトのキーワードを調査する方法
では、具体的にどうやって競合サイトのキーワードを調査するのでしょうか?
主に以下のようなツールと手法が使えます。
競合分析に使える代表的なツール
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| Ahrefs | 競合サイトが上位表示されているキーワード一覧、被リンクも分析可 |
| SEMrush | オーガニック流入の多いキーワード、広告出稿状況も確認可能 |
| Ubersuggest | 無料枠あり。競合ドメインのキーワード可視化に便利 |
| SimilarWeb | サイト全体の流入経路や集客キーワードを分析できる |
これらのツールで競合サイトのURLを入力すると、「どのキーワードで流入があるか」「どのページが読まれているか」「検索順位は何位か」などが一目でわかります。
特に注目すべきなのは、上位表示されていないが検索ボリュームのあるキーワードです。
これは競合がまだ拾いきれていない“隙間”の可能性があり、狙い目キーワードとなります。
上位サイトの構成を真似るのではなく“差別化”する
競合分析で得た情報は、そのまま真似するのではなく、差別化するための材料として使いましょう。
特に以下のような視点が重要です:
- 競合記事にない視点や事例を追加できるか?
- 検索意図をより深く掘り下げられるか?
- 見出し構成や情報の網羅性で勝負できるか?
- 実績・証拠・データなど「E-E-A-T」を補強できるか?
例えば、上位サイトが「SEO対策の基本」しか触れていないなら、自サイトでは「業種別のSEO戦略」や「初心者向けのチェックリスト」など、読者の立場に寄り添った深掘り型のコンテンツを出すことで差別化が可能です。
また、上位サイトのページが古い場合は、最新の情報を加えるだけでも優位に立てることがあります。
競合分析は、「ライバルの弱点を探す」という視点で行うと、思いがけない“ブルーオーシャン”のキーワードが見つかることもあります。
次のブロックでは、そうしたキーワード調査をさらに効率化するための「おすすめツールと活用法」を紹介します。
ツールを活用した効率的な検索ボリューム調査
検索ボリュームの調査を手動で行うのは、時間も手間もかかります。
効率よく、かつ正確にキーワード分析を進めるには、SEOツールの活用が不可欠です。
このブロックでは、無料・有料の代表的なツールの特徴と、どのように使い分けるべきかを解説します。
Googleキーワードプランナーの使い方と活用法
まず必須となるのが、Google広告の公式ツール「キーワードプランナー」です。
無料で使えるうえ、Google検索データに基づいた「月間平均検索ボリューム」「競合性」「入札単価」などが確認できるため、非常に信頼性が高いです。
基本的な使い方:
- Google広告にログイン(アカウント開設は無料)
- 「キーワードプランナー」→「新しいキーワードを見つける」へ進む
- 調べたいキーワードを入力
- 結果として、以下が表示される:
- 月間平均検索ボリューム(例:1,000〜10,000)
- 競合性(低・中・高)
- 想定クリック単価(広告用)
この情報をもとに、検索ボリュームがほどほどで競合性が低いキーワードを優先的に狙う戦略が有効です。
Ubersuggest・KeywordTool・Ahrefsの比較と使い分け
検索ボリュームをチェックするためのツールはGoogleキーワードプランナー以外にも複数存在し、それぞれに得意・不得意があります。ここでは代表的な3ツールを比較してみましょう。
✅各ツールの特徴まとめ:
| ツール名 | 特徴 | 無料利用範囲 |
|---|---|---|
| Ubersuggest | シンプルでUIがわかりやすく、検索数とSEO難易度が見られる | 1日3回まで無料(登録で拡張可) |
| KeywordTool.io | サジェストキーワードを大量に取得できる | ボリューム表示は有料 |
| Ahrefs | キーワードだけでなく、競合分析、被リンクチェックも可 | 有料のみ(高機能) |
Ubersuggestは初心者におすすめで、直感的に検索ボリュームや競合性がチェックできます。
一方で、深い分析(競合や被リンク)まで行いたい場合はAhrefsが圧倒的に優秀です。
キーワードの分類とグルーピングのコツ
ツールで集めたキーワードは、ただ列挙するのではなく、目的別にグループ分けして整理することが重要です。以下のように分類すると、コンテンツ設計にも役立ちます。
グルーピング例:
| カテゴリ | キーワード例 | 用途 |
|---|---|---|
| 情報収集型 | 「SEOとは」「WEBサイト 作り方」 | ブログ記事や用語集に向く |
| 比較検討型 | 「ホームページ制作 比較」「CMS 比較」 | 中間CVを狙えるLPや記事に活用 |
| 行動誘導型 | 「ホームページ制作 名古屋 依頼」 | 問い合わせ・資料請求を誘導するページに使う |
グルーピングされたキーワードを使って、構成案・目次・内部リンク設計を先に立ててから執筆を始めると、SEO効果がさらに高まります。
ツール活用の注意点
どのツールも万能ではありません。
ツールによって検索ボリュームの数値が微妙に異なることもあります。
これは、各社の計測方法やアルゴリズムに差があるためです。
そのため、検索ボリュームの数値は「絶対値」ではなく「傾向」として参考にすることが大切です。
また、数字よりも「検索意図」「競合の弱さ」「自社との親和性」を重視しましょう。
SEO対策において、検索ボリュームの調査は時間対効果の高い作業です。
適切なツールを使いこなすことで、効率よくキーワード設計ができ、成果につながるコンテンツ作成に直結します。
キーワード選定からSEO施策へつなげるポイント
検索ボリュームの調査とキーワード選定が完了したら、次にやるべきは、それを実際のSEO施策にどう活かすかという工程です。
いくら良いキーワードを見つけても、それをWEBサイト上で適切に使わなければ意味がありません。
このブロックでは、キーワードをコンテンツに反映する方法、SEOとしての効果を最大限にするための配置・構造・内部リンク戦略までを、実践的に解説します。
キーワードは「配置」が命。正しい設置場所とは?
選定したキーワードをWEBページ内に配置する際、ただ本文中に散らすのではなく、SEO効果の高い場所に的確に配置することが重要です。
配置すべき主なポイント:
| 配置箇所 | 意図・効果 |
|---|---|
| タイトル(titleタグ) | 検索順位にもっとも影響する重要要素 |
| 見出し(h1, h2, h3) | ページ構造をGoogleに伝えるために重要 |
| URLスラッグ | 短く、キーワードが含まれていると好影響 |
| メタディスクリプション | クリック率に影響(順位には直接関係なし) |
| 本文の冒頭・文末 | ユーザーとGoogle双方に「テーマ」を伝える |
Point: キーワードの詰め込みすぎには注意。
「自然な文脈で、ユーザーにとって意味のある使い方」が基本です。
内部リンクでキーワードの“文脈”を作る
SEOでは、1ページ単体ではなく、サイト全体でのテーマの一貫性が評価されるようになっています。
そのため、関連性の高いページ同士を内部リンクでつなぐことで、「このサイトはこのテーマに強い」とGoogleに伝えることができます。
内部リンク戦略の例:
- 「SEO 初心者」という記事から「SEO キーワード選定」記事へのリンク
- 「ホームページ制作 名古屋」から「WEBデザイン事例」へのリンク
- 「CMS 比較」から「WordPressのメリット」へのリンク
これにより、検索意図に沿ったサイト構造(トピッククラスター)が構築され、回遊率も向上します。
E-E-A-Tとキーワードの関係も意識する
Googleが評価指標として重視する「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」においても、キーワードとの関連性は重要です。
たとえば「SEO対策 おすすめ」といったキーワードで上位を狙うなら、単なる情報の羅列ではなく、
- 過去の施策事例(経験)
- 専門家の監修(専門性)
- 他メディアへの掲載歴(権威性)
- 引用・参考文献(信頼性)
といった要素をページ内で明確に打ち出すことで、Googleからの評価もユーザーの信頼も獲得できます。
キーワード設計をページ設計・サイト設計に昇華させる
最終的には、キーワード選定を「記事単体」ではなく、サイト全体の構成・情報設計へと統合することが理想です。
たとえば、以下のように「軸となるキーワード」を中心に記事を展開する設計が有効です:
キーワード中心のサイト設計例:
コピーする編集するSEO対策(ビッグキーワード)
├─ SEO キーワード選定(ミドル)
│ └─ SEO キーワードツール(ロングテール)
├─ SEO 初心者(ミドル)
│ └─ SEO 内部対策 方法(ロングテール)
├─ SEOとは(情報型)
このようにトピックごとに深堀り記事を構築し、内部リンクでつなげておくことで、SEO効果を長期的に蓄積できる構造が完成します。
キーワードは、単なる「言葉」ではなく、ユーザーの意図・行動・心理を読み解くための入り口です。検索ボリュームという“数字”を出発点に、サイトの構造・コンテンツ戦略・導線設計に落とし込むことで、WEBサイト全体が戦略的に機能しはじめます。